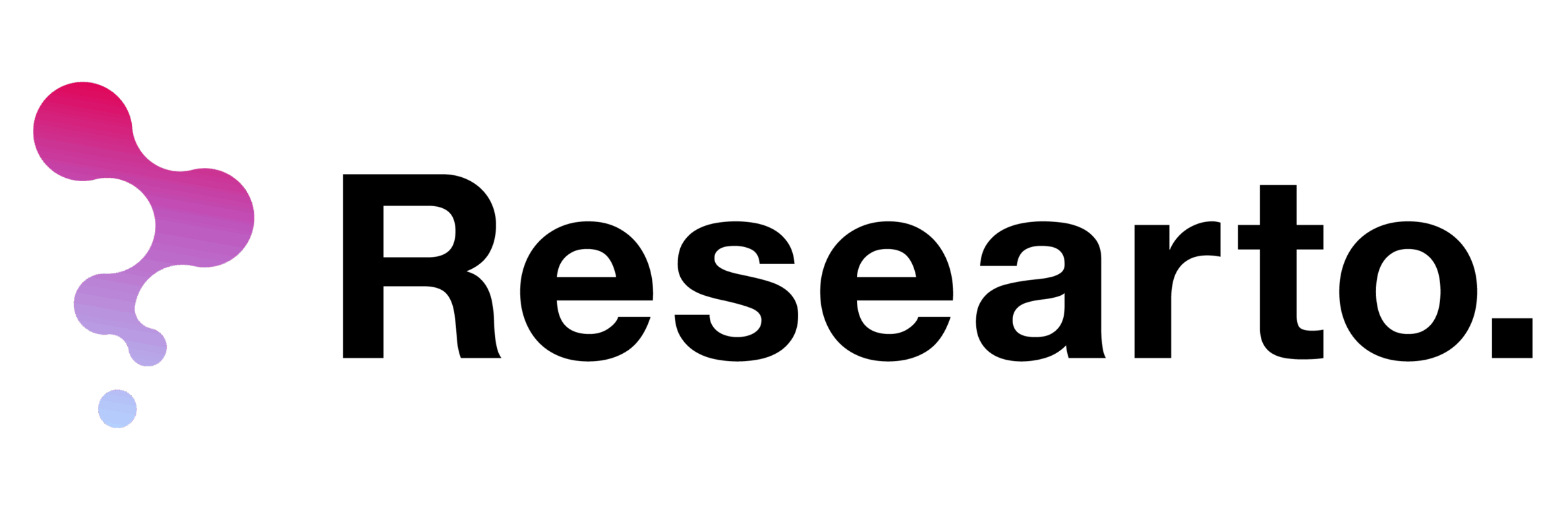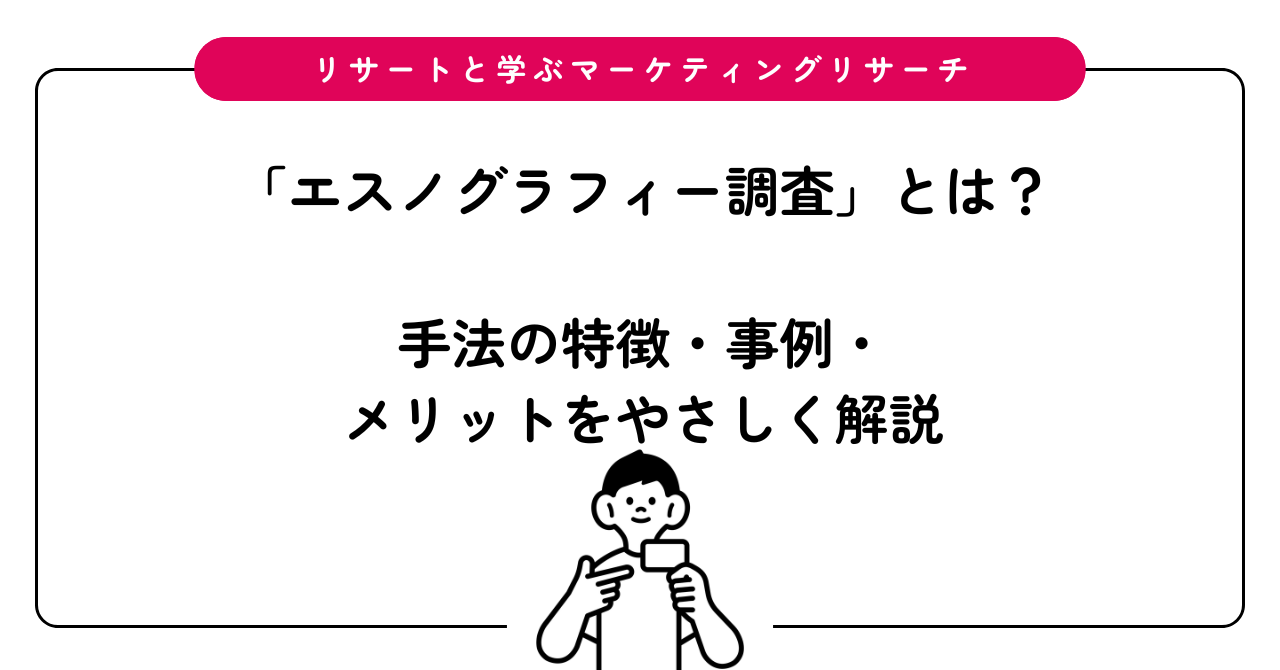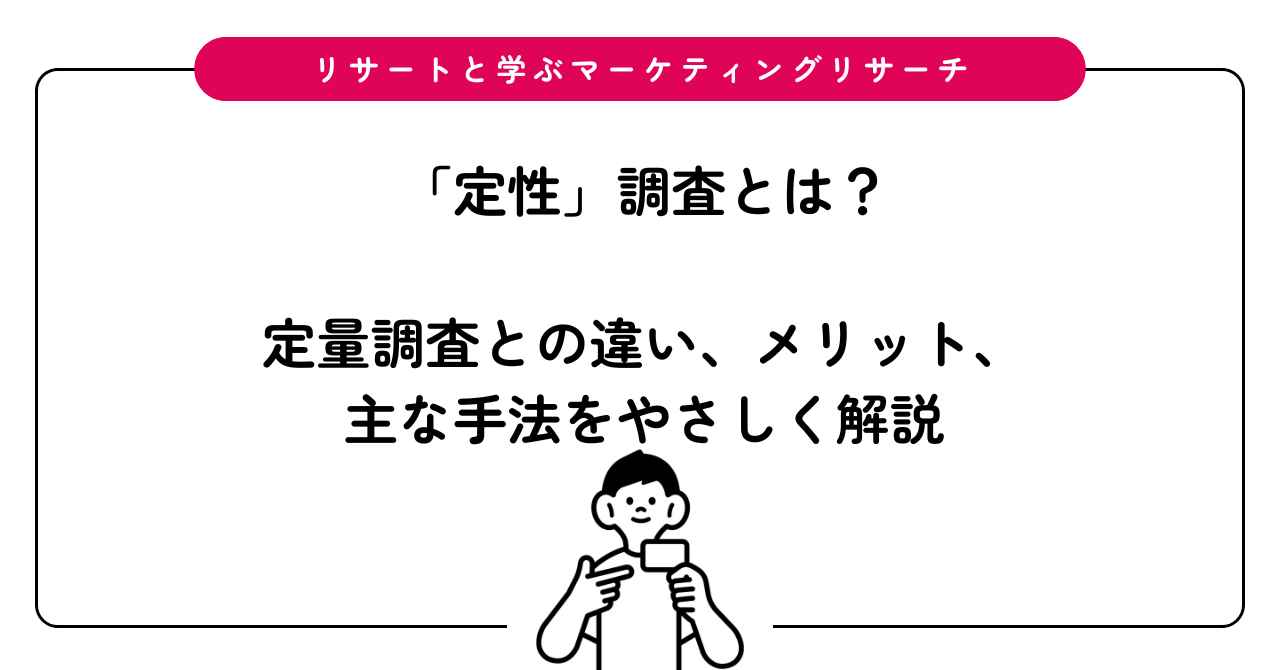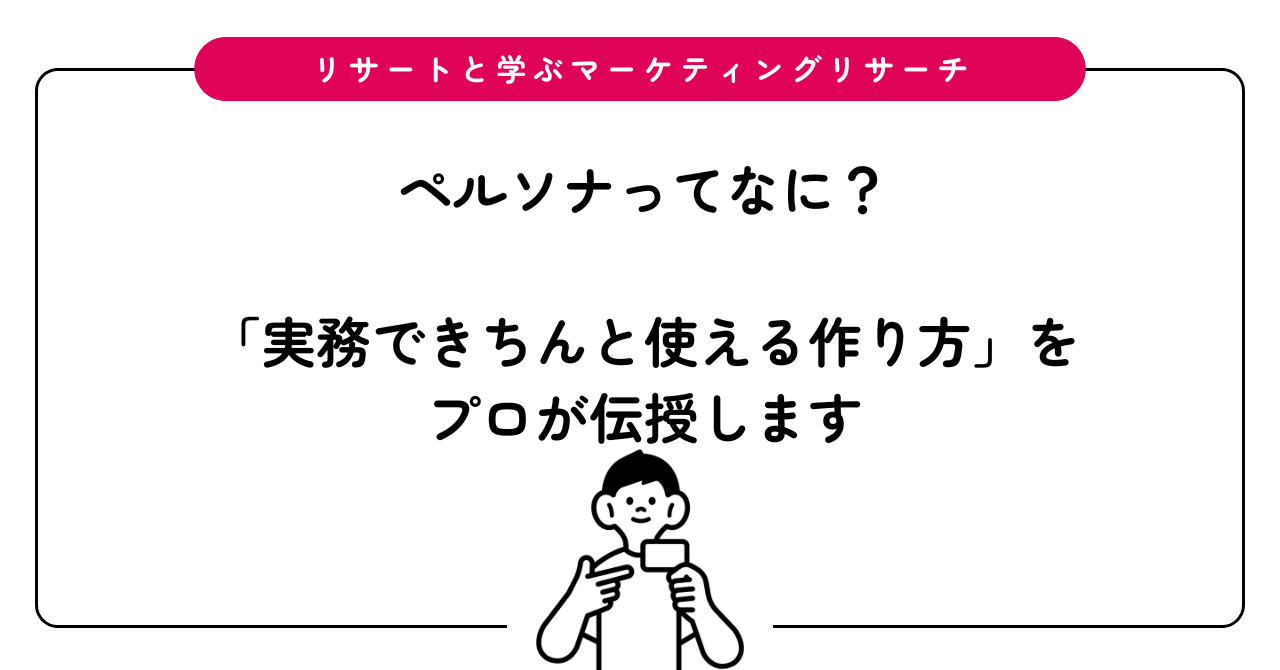近年、ユーザーや生活者の“リアルな行動”を深く理解するための調査手法として注目されているのがエスノグラフィー調査(行動観察調査)です。
アンケートやインタビューといった一般的な調査では捉えきれない「無意識の行動」「言語化されないニーズ」を明らかにできるため、UX改善や商品開発、マーケティング戦略の構築に広く活用されています。
本記事では、エスノグラフィー調査の定義や特徴、実施手順、活用事例、メリット・デメリット、そして成功させるためのポイントまでを網羅的に解説します。
エスノグラフィー調査とは(行動観察調査の基本)
エスノグラフィーの定義
エスノグラフィー(Ethnography)とは、もともと文化人類学において民族や文化を理解するために用いられた調査手法です。
マーケティングにおけるエスノグラフィー調査は、定性調査の一種で対象者が普段過ごしている自然な環境に入り込み、行動や発言、使用状況を観察・記録して分析する方法を指します。
エスノグラフィー調査が注目される背景
デジタル時代の今、消費者は多様なチャネルやツールを利用して商品やサービスを選択しています。こうした行動は必ずしも本人が自覚的に説明できるとは限らず、アンケートやインタビューでは見落とされることも少なくありません。
現場での観察により、ユーザーの本当の使い方や感情を把握できる点が、エスノグラフィー調査の最大の魅力です。
エスノグラフィーと他の定性調査の手法の違い
| 調査手法 | 特徴 | 得られる情報 |
|---|---|---|
| エスノグラフィー調査 | 現場での行動観察 | 無意識行動、文脈、習慣 |
| デプスインタビュー | 1対1で深掘り | 意識的な価値観や感情 |
| 定量調査 | アンケートや統計分析 | 数値化された傾向・割合 |
あわせて読みたい:エスノグラフィー調査の記事はこちらから
エスノグラフィー調査が有効な理由
無意識行動やサイレントデータの発見
人は、自分がなぜその行動を取っているのかを常に自覚しているわけではありません。観察を通して、対象者が言葉では説明できない行動や習慣(サイレントデータ)を収集できます。
質問では得られない深い洞察
アンケートやインタビューでは事前に用意した質問に沿った情報しか得られません。エスノグラフィー調査では、予期せぬ行動や感情を現場で発見し、新しい仮説やアイデアにつなげられます。
エスノグラフィー調査の実施手順【6ステップ】
STEP1. 調査目的と仮説の設定
まずは「何を明らかにしたいのか」を明確化します。例:新商品の使用シーン把握、UX改善のための課題発見など。
STEP2. 対象者と観察環境の選定
ターゲットユーザー像に合致する被験者を選び、家庭・職場・店舗など自然な環境で調査します。
STEP3. 観察計画と記録方法の設計
観察時間、記録方法(映像・写真・メモ)を決定。許可やプライバシー配慮も重要です。
STEP4. 現地観察・フィールドワーク
対象者の行動をできるだけ介入せずに観察。会話や動作、使っている製品やツールも記録します。
STEP5. データ整理と分析
観察記録を整理し、共通パターンや特徴的な行動を抽出します。写真や映像は分析の補助資料として活用します。
STEP6. 結果の共有と活用
分析結果を関係者に共有し、商品改良やUI設計、マーケティング施策に反映します。
エスノグラフィー調査の活用事例
UX・UIの改善
アプリ利用者の操作を観察し、利用時に発生する迷いやストレスを特定。UI改善につなげる。
新商品開発・既存商品の改善
家庭での調理行動を観察し、使いやすさや不便な点を洗い出して新商品の開発に反映。
マーケティング戦略の策定
店舗での購買行動を観察し、棚配置や販促物の改善アイデアを得る。
カスタマージャーニーの作成・FMOT調査
ペルソナの作成
エスノグラフィー調査のメリットとデメリット
メリット
- 無意識の行動やニーズを発見できる
- 文脈や背景を深く理解できる
- 新たなアイデアや仮説を生みやすい
デメリット
- 実施に時間とコストがかかる
- 観察者のバイアスが入りやすい
- 対象者数が限られるため一般化しにくい
エスノグラフィー調査を成功させるポイント
- 調査前に目的と仮説を明確にする
- 観察者のスキル向上とバイアス回避
- プライバシーと倫理面の配慮
- 関係者と結果を共有し活用までつなげる
まとめ:エスノグラフィー調査で得られる価値
エスノグラフィー調査は、従来の質問型調査では捉えられない深い洞察を得られる強力な手法です。
「ユーザーの本当の姿」を理解し、商品やサービスの改善、そして新たな価値創造につなげるために、今後ますます重要性が高まるでしょう。