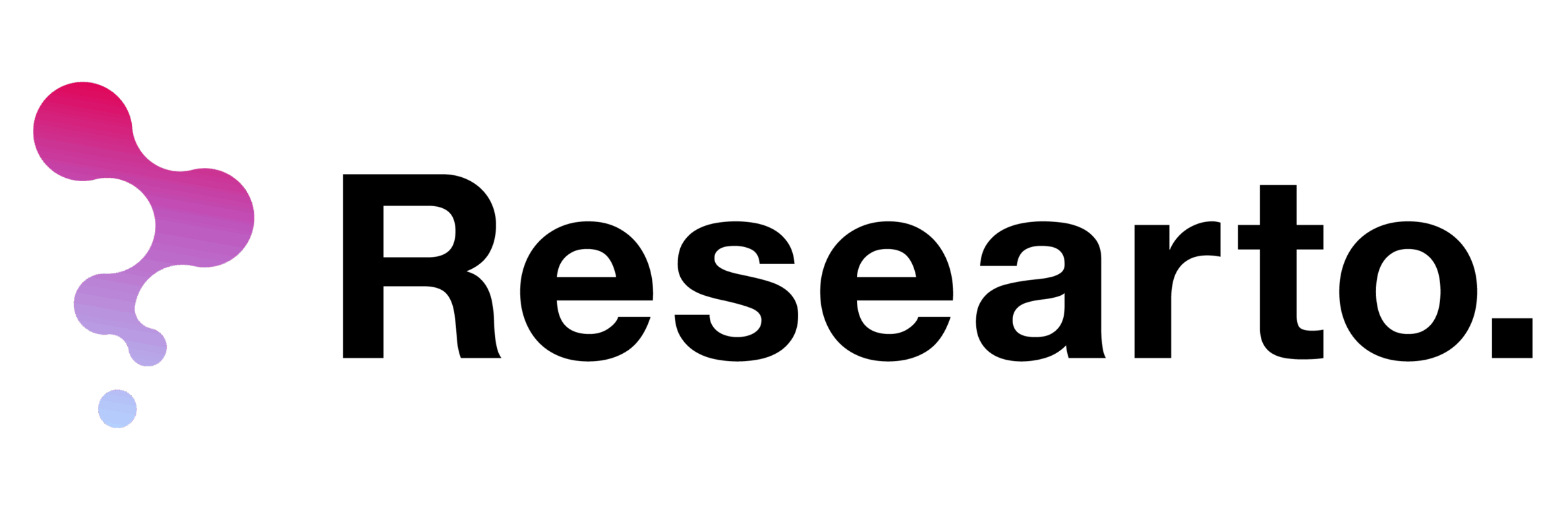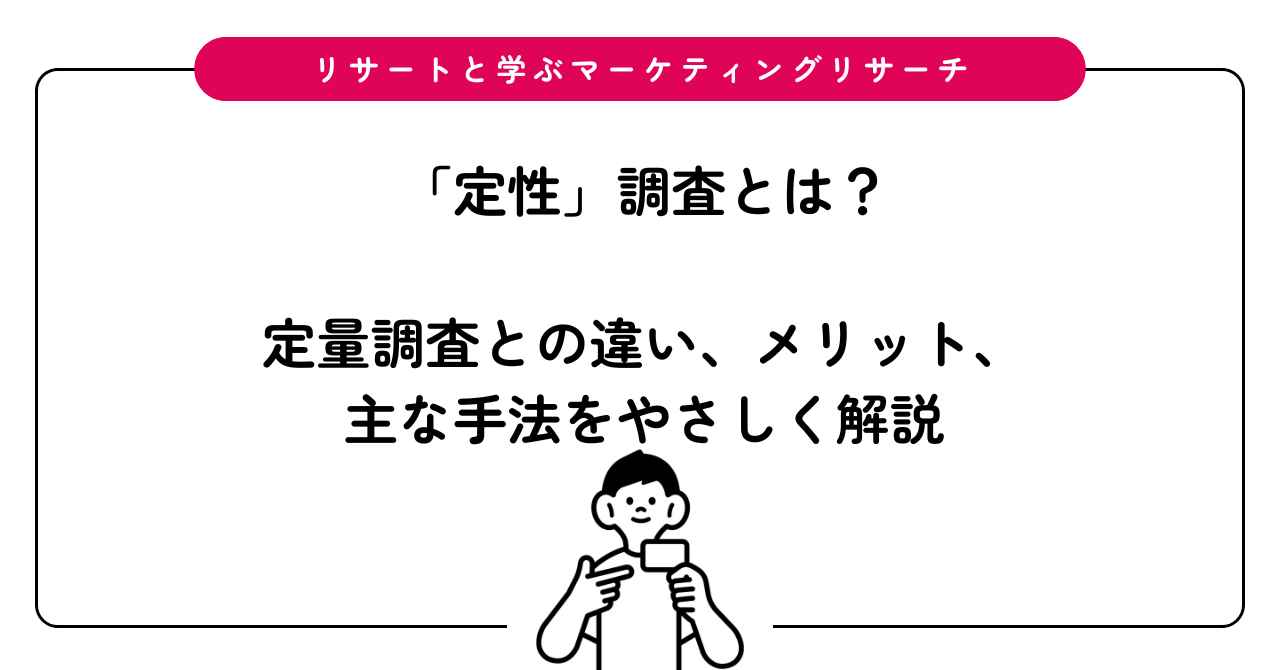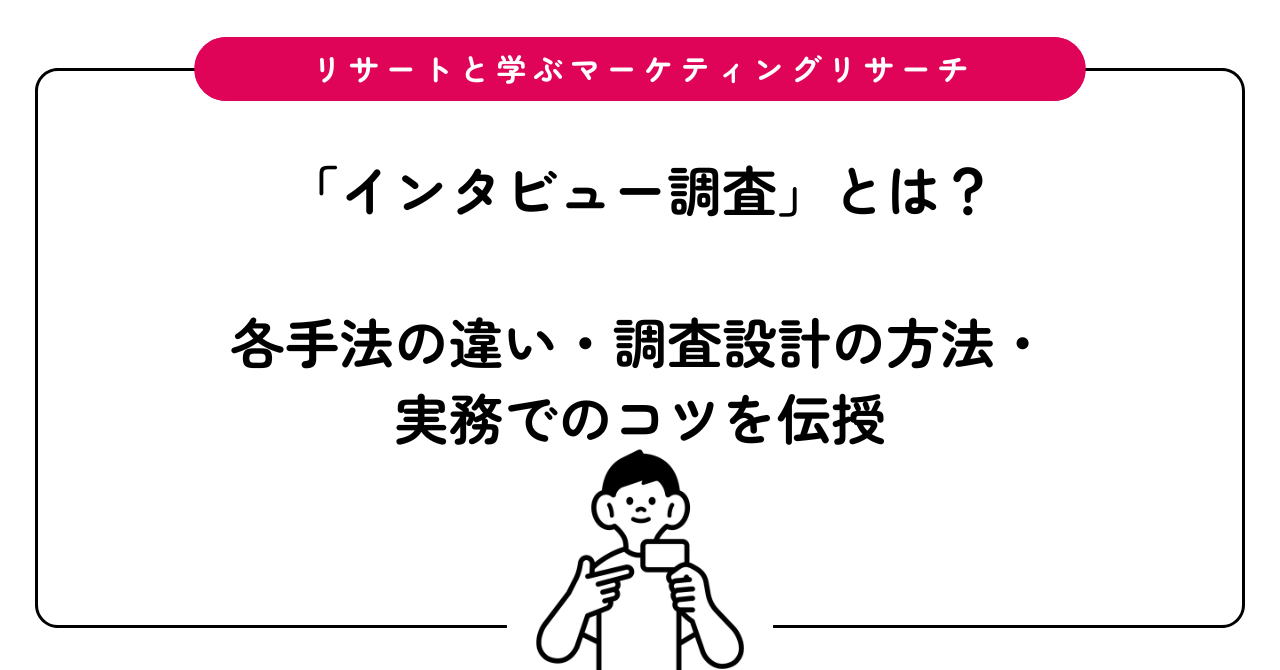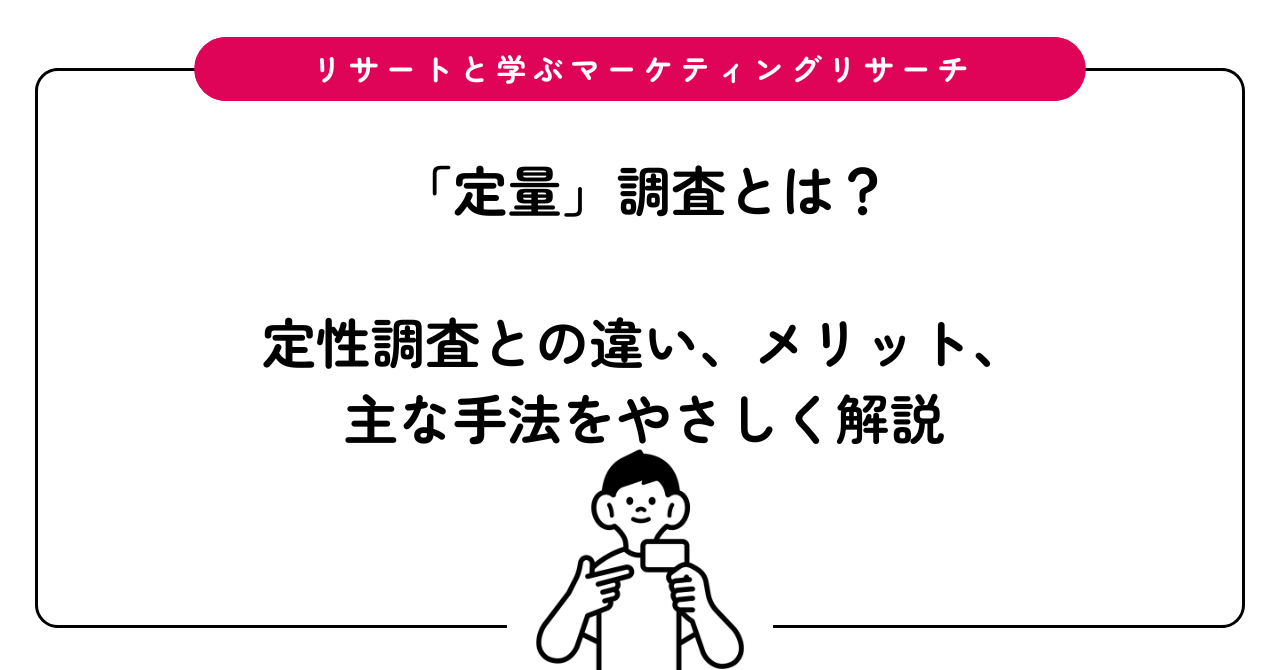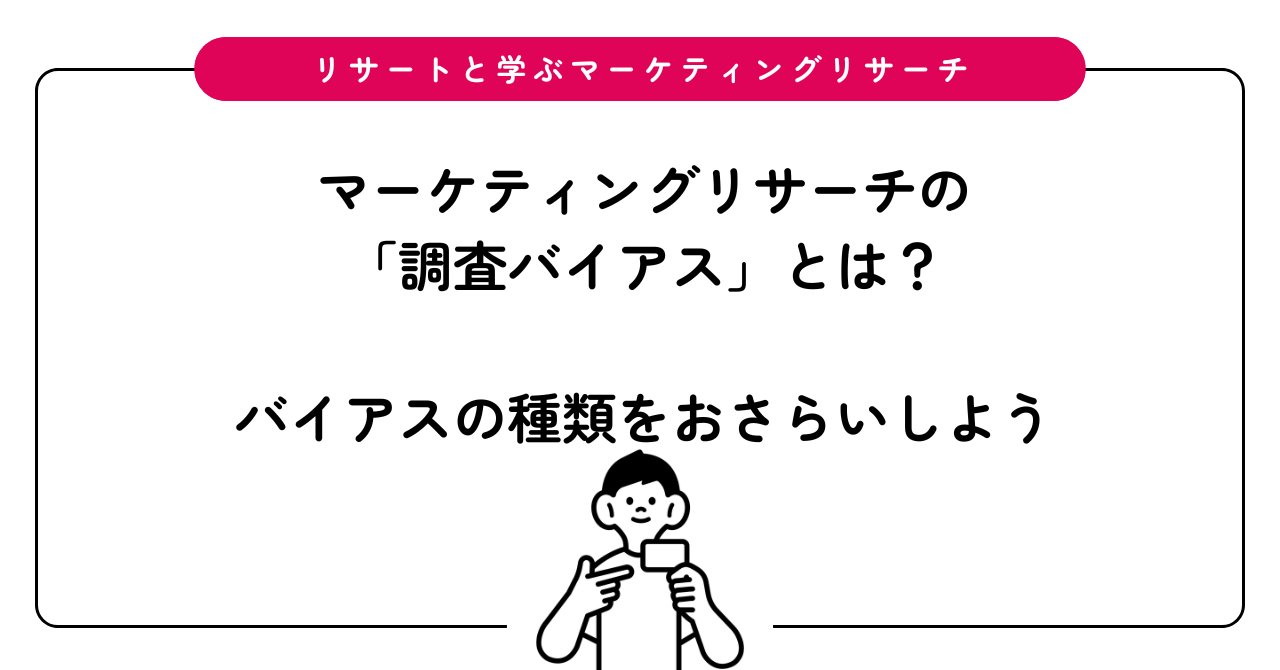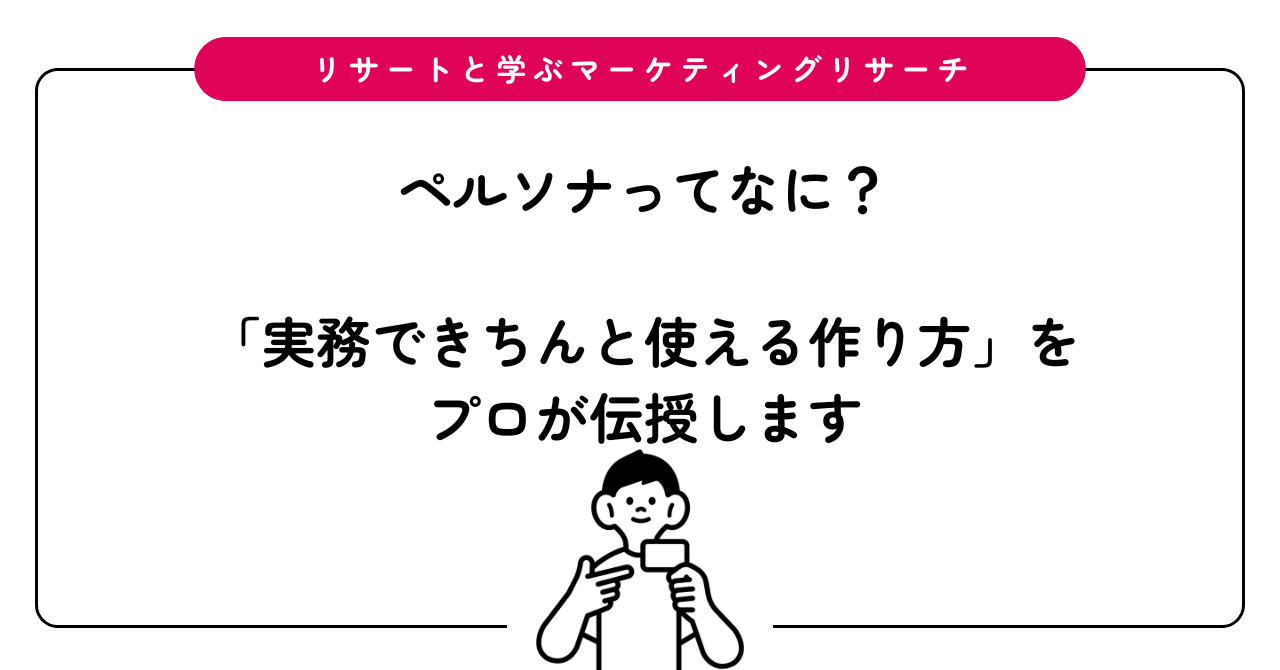はじめに
マーケティングや製品開発、ユーザー理解を深めるうえで欠かせないのが「消費者調査」「マーケティングリサーチ」です。その中でも、顧客の“生の声”や“本音”を深く探るために用いられるのが「定性調査」です。
この記事では、定性調査の意味や定量調査との違い、メリット・デメリット、具体的な手法までを初心者にもわかりやすく解説します。定性調査を検討中の方や、より深い顧客理解を目指したいマーケターやマーケティングリサーチャーにとって、有益な情報をお届けします。
定性調査とは?その意味と特徴
定性調査とは、数値では表せない人の意見や感情、価値観、動機などの「質的な情報」を深掘りして把握する調査手法です。
- 「なぜそう思ったのか?」
- 「どのように感じたのか?」
- 「どんな背景や価値観があるのか?」
といった、人間の内面に迫る情報を得ることが目的です。
定性調査の主な特徴
- 数値化せず、言語情報を中心に分析する
- 小規模な対象者(数名〜数十名)に深くインタビューや観察を行う
- 分析はパターンや傾向を見つける“解釈型”
定量調査との違いは?比較で理解しよう
定量調査と定性調査の違い
| 比較観点 | 定量調査 (Quantitative) | 定性調査 (Qualitative) |
|---|---|---|
| 目的 | 実態の「検証」 市場規模の「測定」 | 仮説の「発見」 背景文脈の「理解」 |
| 問いの性質 | How many?/How much? (どれくらい?) | Why?/How? (なぜ? どのように?) |
| アウトプット | 数値 (回答率、平均値など) | 言葉 |
| 代表的な手法 | インターネット調査 (Webアンケート調査) 会場調査(CLT) ホームユーステスト(HUT) 海外調査(ネットリサーチ) | インタビュー調査 ・グループインタビュー ・デプスインタビュー ・エスノグラフィー調査 |
| 分析視点 | 統計的推測 全体傾向の把握 セグメンテーション | インサイトの抽出 因果メカニズムの解明 |
| リスク | 「想定外」を拾えない (選択肢にない答えは0になる) | 「一般化」が難しい (n=1の声が全体とは限らない) |
両者は目的や扱うデータが大きく異なりますが、補完的に活用することで、より立体的なマーケティング判断が可能になります。
定性調査のメリット
1. 深いインサイトの発見ができる
表面的な回答ではなく、「なぜそう思うのか?」という心理の深層に迫ることができ、商品開発やコミュニケーション施策のヒントにつながります。
2. 想定外のニーズや課題に気づける
あらかじめ用意された選択肢では出てこない、ユーザー独自の視点や行動パターンが見えてくるのも定性調査ならではです。
3. 商品やサービスへの“リアルな声”を聞ける
顧客の言葉や感情を直接聞くことで、数字では見えない「共感」や「違和感」を把握できます。
定性調査のデメリット・注意点
- サンプルサイズが小さいため、一般化しにくい
- インタビュー実施や分析に時間が必要
- 分析者の主観に左右される可能性がある
- 分析の難易度が定量調査よりもはるかに高い
これらの特性を理解したうえで、目的に合った手法を選ぶことが重要です。
あわせて読みたい:定性調査の難しさ:調査バイアス
主な定性調査の手法
1. デプスインタビュー(IDI, In-depth Interview)
デプスインタビューは、1人の対象者に対し、インタビュアーが深掘り質問を行う手法のことです。パーソナルな意見や本音が引き出しやすいのが特徴です。
海外のマーケティングリサーチ業界ではインデプスインタビュー呼びます。
2. フォーカスグループインタビュー(FGI, Focus Group Interview)
フォーカスグループインタビューは、3〜8名程度のグループに対し、モデレーターがテーマに沿って進行する座談会形式。複数人の相互作用により多様な意見が得られます。
3. エスノグラフィー調査(行動観察調査, Ethnography)
エスノグラフィー調査は、実際の利用場面を観察しながら、対象者の無意識的な行動や習慣を把握する手法。UX調査や店舗調査で活用されます。
代表的な手法はホームビジットとショップアロングです。(今後解説予定)
4. 日記調査・写真調査
日常の体験を記録してもらうことで、リアルな生活背景や使用シーンを把握する方法です。
定性調査の活用シーン
- 新商品やサービス開発のコンセプト検討
- ターゲット顧客のインサイト把握
- ブランドイメージや広告表現の評価
- UI/UXの改善ポイント発見
- カスタマージャーニーの作成
- ペルソナの作成
定性調査は「課題の発見」や「仮説構築」に特に有効です。その後、定量調査で検証するという流れが一般的です。
カスタマージャーニーを作成する際や、ペルソナを作成する際は、定性調査を活用することが多いです。
あわせて読みたい:プロのカスタマージャーニー・ペルソナの作成の仕方
まとめ
マーケティングや企画業務において、「ユーザーの心の奥を知りたい」「定量では見えない背景を理解したい」と感じたときこそ、定性調査の出番です。
目的に応じて、適切な調査設計とスキルをもって実施すれば、ビジネスを前進させるための大きなヒントが見えてくるはずです。
あわせて読みたい:定性調査の代表的な手法:インタビュー調査のやり方
あわせて読みたい:定量調査とは?
リサートは定性調査が得意なマーケティングリサーチ会社です
この記事の監修者

角 泰範 | マーケティング・リサーチャー
リサート所属モデレーター。シンクタンク・マーケティングリサーチ複数社を経て現職。マーケティングリサーチャーとして10年以上の経験を有し、大手ブランドの広範な商材・サービスの調査を支援。統計学的な分析手法とインタビューをハイブリッドに活用した、定量・定性の両軸での消費者分析力が強み。
この記事を書いた人

石崎 健人 | 株式会社バイデンハウス マネージング・ディレクター
リサート所属モデレーター。外資系コンサルティング・ファーム等を経て現職。バイデンハウスの消費財、ラグジュアリー、テクノロジー領域のリーダーシップ。生活者への鋭い観察眼と洞察力を強みに、生活者インサイトの提供を得意とする。2022年より株式会社バイデンハウス代表取締役。2025年よりインタビュールーム株式会社(リサート)取締役。アドタイにてZ世代の誤解とリアル。「ビーリアルな、密着エスノ記」連載中。