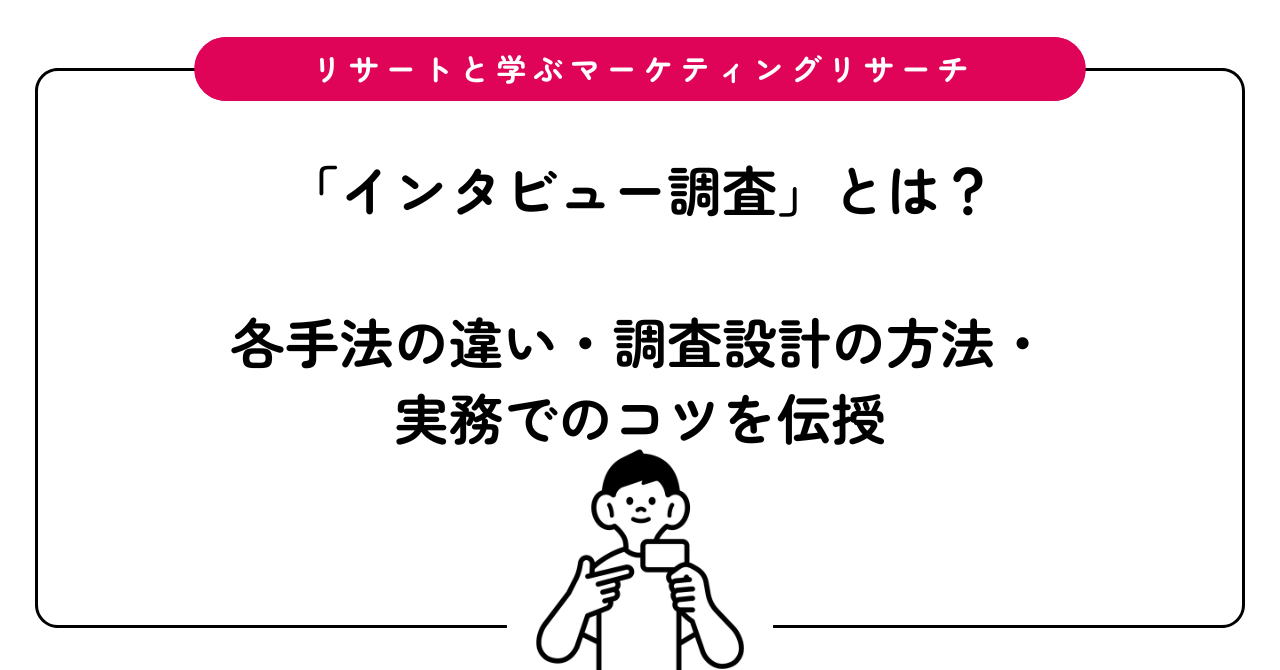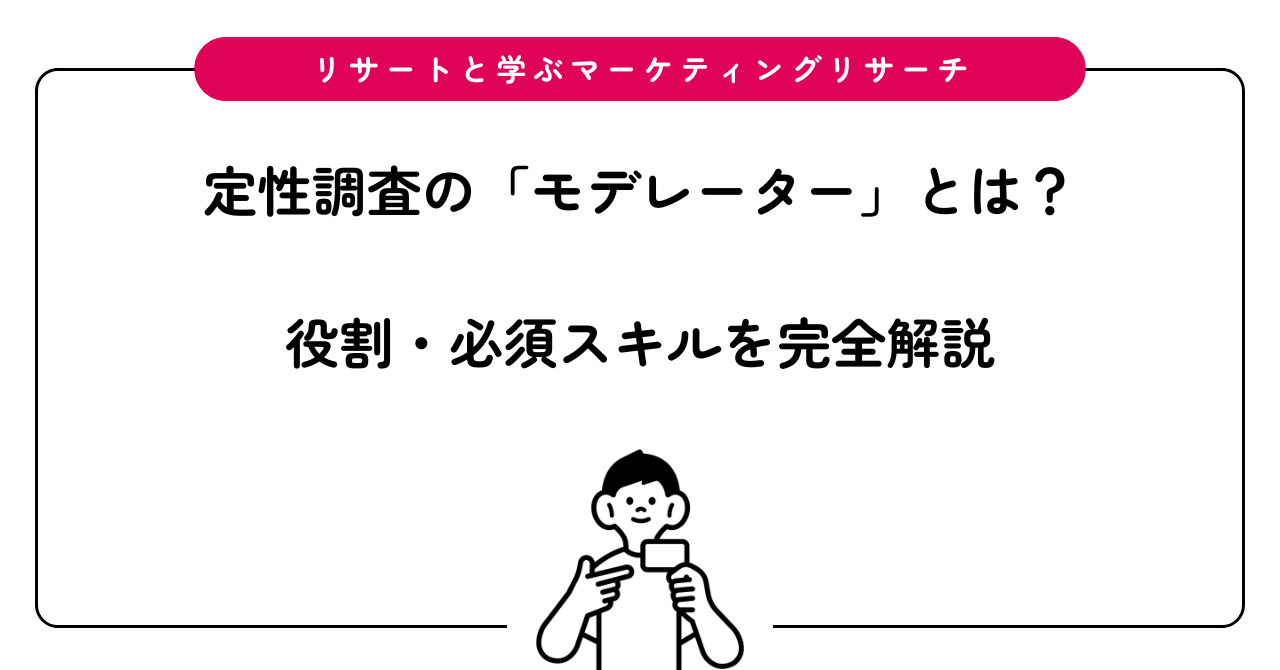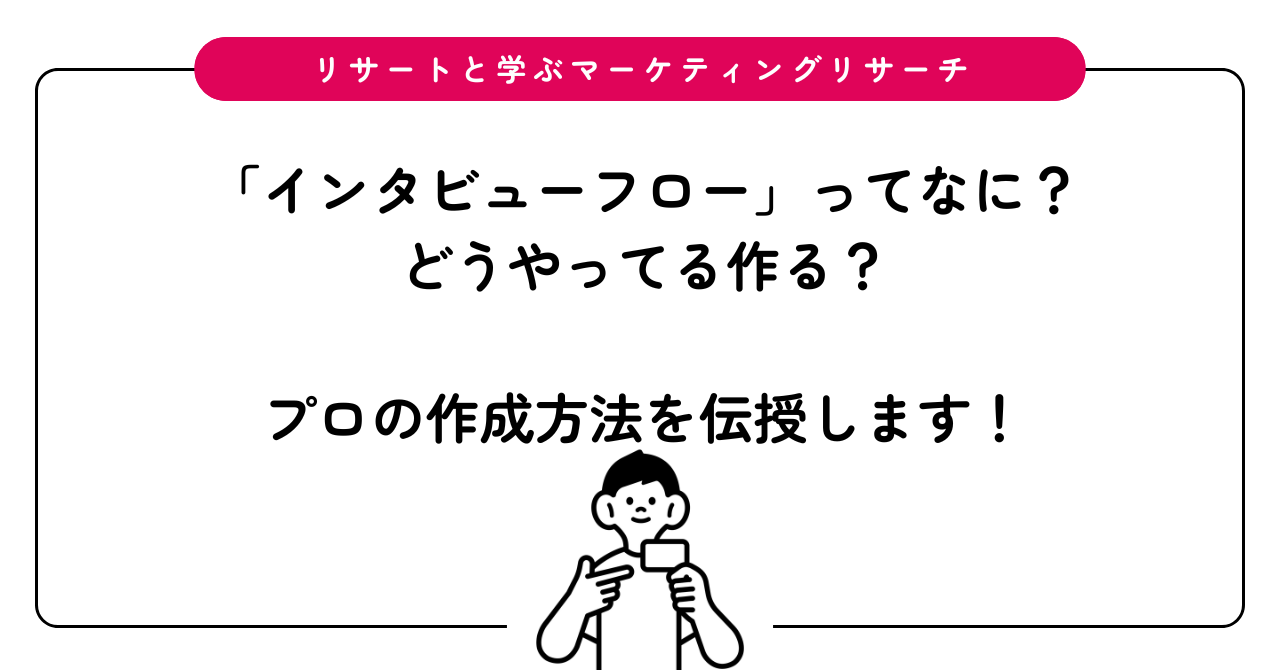筆者はモデレーターとして定性調査を進行する中で、インタビューの冒頭をどのように設計するかによって、会話のテンポや話題の広がりが大きく変わることを繰り返し体感してきました。質問設計や分析計画と同じくらい、冒頭のつくり方は重要です。参加者が最初に「どんな場か」「どう話せばよいか」「何を期待されているのか」を判断するのが冒頭だからです。ここで構えが残ると、その後の会話が硬くなり、経験の語りが出にくくなります。
筆者が重視しているのは、冒頭が「調査の準備運動」ではなく、参加者が自然なペースに戻るための大切な工程であるという観点です。参加者は初対面の環境に置かれ、自分の発言がどのように扱われるかを探っています。こちら側が説明していない期待を読み取ろうとしたり、評価されないかを気にしたり、無意識の緊張が続く状態です。この心理状態に対して、適切な働きかけを行うのが冒頭の役割だと筆者は考えています。
しかしながら、インタビューの冒頭の部分は軽んじられがちです。そのため、冒頭の時間を短くして欲しいというリクエストは意外と多いものです。そこで本稿ではインタビューの冒頭部分についてどのように進めていけばよいかをお伝えしていきたいと思います。
アイスブレイクとラポール形成は役割が違う
筆者は、インタビュー調査の冒頭でしばしば語られる「アイスブレイク」と「ラポール形成」を混同しないよう注意しています。
アイスブレイクとは、参加者が「声を出すこと」に対する抵抗を減らす工程です。移動の様子、会場の気温、直前に見たニュースなど、考えなくても答えられる話題を短く扱います。目的は場を温めることではなく、参加者が口を開いてみる機会をつくることです。ほんの2〜3分で十分です。人によってはインタビュー開始前に簡単に挨拶をする形で行う人もいますね。
一方、ラポール形成とは、参加者が「話してよい」と判断できる状態をつくる工程です。評価されない安心感、正しい答えを探さなくてよいという許可、自由に話せる空気づくりなど、心理的な準備を整えるための働きかけです。この準備が整うと、参加者は生活場面を思い出しながら自然な口調で語り始めます。
ラポール形成がされた状態とは、インタビュー参加者にて以下が実現されている状態のこと。
- 自分の発言に対して質問者から評価されない安心感がある
- 世の中一般的に正しい答えを探さなくてよいという許可を感じている
- 自分が思ったことを自由に話してもよいという包摂を感じている
- 自分の発言が公共の場に漏れることはないという心理的安全性を感じている
- 自分の発言に対して不快感のある反応がこない確証を得られている
筆者は、アイスブレイクが多少うまくいっても、ラポール形成が不足すると本題で語りが急にたどたどしくなる場面を何度も見てきました。和やかな雰囲気でも、参加者はまだ警戒していることがあります。アイスブレイクは「声の準備」、ラポール形成は「心の準備」。この二つが揃って初めてインタビューは進めやすくなります。
インタビュー調査冒頭で避けたいことは、抽象的な自己分析を迫る導入
筆者が最も避けている導入は、抽象的な自己分析を迫る質問です。海外の調査会社や、海外手法に影響された現場で次のような質問が使われる場に何度も立ち会いました。
海外の定性調査でよく見かける、日本では機能しづらい導入
- 「自分を三つの特徴で表すなら?」
- 「自分の性格を一言で説明するなら?」
- 「自分を何かに例えると?」
これらは心理テストのように聞こえますね。初対面の場でいきなり求められると、多くの参加者が身構えます。「どう答えるのが正しいか」を考え始め、表情が硬くなり、声も弱まり、インタビューの流れが重くなります。
筆者の経験・観察では、このような導入を使った場では、その後の語りも慎重になりがちです。経験の描写よりも、場に合いそうな答えを探す発言が増え、テーマに関する判断の背景が出てこなくなります。
一見すると場を盛り上げる効果がありそうですが、実際にはインタビューの進めやすさを損なう危険な導入です。また、抽象的な自己分析を迫る導入は時間もかかるので、予定時間よりもオーバーしてしまう可能性が高いです。
なぜ海外のインタビュー調査では抽象的な導入が好まれるのか
筆者は海外調査会社と協働した経験から、抽象的導入が好まれる理由は文化的な違いにあると考えています。
欧米圏では、自己表現が日常のコミュニケーションに組み込まれています。学校教育でも、自分の価値観を説明する、自分を象徴するキーワードを挙げる、といった訓練が日常的に行われています。そうした文化圏では、抽象的な自己紹介は負担ではなく、「自分を共有する自然な手段」として受け入れられやすいのかと思います。
また、欧米のリサーチ文化には、最初に参加者の価値観や性格を把握し、分析に活かすというプロファイリングの考え方があるようです。抽象的導入はそのための手がかりとして位置づけられており、参加者も慣れているようです。
しかし、日本では状況が違います。日本の生活者は、自己分析よりも「場に適応すること」を優先する傾向があります。抽象的な導入は回答の負荷が高く、「うまく答えなければ」と緊張させてしまい、自然な会話から遠ざかります。特に就職活動を経ている人は、自分を何かに例えたり、自分を表現する言葉を用意していたり、自分がそうであるように振舞う感覚があるように思います。
筆者は、日本の生活者に対して海外と同じ導入を使うことは、ほとんどの場合おすすめできないと感じています。
インタビュー調査の自己紹介は事実の情報に限定するのが最も自然
筆者がインタビュー調査の冒頭で必ず採用しているのが、事実情報だけを尋ねる自己紹介です。
- 姓(個人情報の取り扱いの観点から姓だけの方が望ましいです)
- 年齢
- 居住エリア(県/市)
- 家族構成
- 職業
- 趣味/最近ハマっていること
これらは答えやすく、比較される不安もなく、生活文脈も自然に伝わります。参加者が緊張しがちな冒頭でも、負荷がほぼゼロで話せる形式です。筆者は「考えなくても答えられる質問」で自己紹介を構成することを徹底しています。
何度か抽象的な導入を試みた場に立ち会いましたし、筆者自身も依頼主のリクエストでトライしてみましたが、参加者が考え込み、表情が固まり、その後も慎重な姿勢が続きました。もちろん、スラスラと喋ってくださる参加者もいましたが、海外の調査会社の方が期待しているような回答はあまり得られなかった印象を受けました。これらの経験から、自己紹介は事実情報だけに絞るのが最も自然だと確信しています。
クライアントから「インタビュー調査の冒頭は5分で」と言われがちな理由
筆者がインタビュー調査の現場で頻繁に直面するのが、クライアントからの「冒頭をもっと短くしてほしい」という要望です。ときには「5分以内でお願いします」と具体的に言われることもあります。
この要望が出る背景には次のような理由があります。
インタビュー調査の冒頭は手短でよいと誤解されている理由
- 冒頭が雑談だと誤解されている
- インタビュー調査は時間が限られているため、本題にできるだけ時間を使いたい
- 目的説明も簡潔でよいなら、導入全体を短縮できると考えられている
しかし筆者は、冒頭を削りすぎると逆に本題が進めにくくなると感じています。理由は三つです。
インタビュー調査の冒頭を手短にしてはいけない理由
- インタビュー調査の冒頭は雑談ではなく、参加者の構えを緩め、話しやすい状態に整えるための工程だからです。ここを削ると、参加者はまだ“慎重モード”のまま本題に入ることになり、語りが出にくくなります。
- インタビュー調査の冒頭の短縮は、発話ペースのばらつきを生みます。参加者同士の距離感が整わず、特にフォーカスグループでは発言の偏りが生まれやすくなります。
- 結果として本題の情報量が減るケースが多いことです。筆者は、冒頭で参加者の緊張が十分にほぐれた場ほど、本題での語りが自然で量も増えることを繰り返し観察してきました。
短くすべきは不必要な演出であり、心理的準備の工程そのものではありません。
また、冒頭の導入パートでモデレーターが説明するインタビュー目的/録画録音に関する同意/守秘義務/個人情報の取り扱いなどの説明を来場時に運営側が説明することで短縮したいという方もいらっしゃいますが、運営側がする説明とモデレーターがする説明は同じ内容であっても目的が異なります。
調査会社が対象者の来場時に説明するのは注意事項などであって、何かあった際のリスクヘッジを目的としています。一方で、モデレーターがする同意事項の説明は対象者に対する信頼獲得を目的としています。いきなり信頼獲得はできなくても害意はないということを理解してもらうために行っています。
調査目的の説明は「方向性だけ」に留める
昨今はセルフリサーチのサービスが普及していることもあり、インタビューの内製化を進めている企業も増えてきました。そのため、インタビューの冒頭でどんな話をすればよいかがわからず、インタビュー調査の目的の説明を「プロジェクトの目的」と誤解して、つい「企業の課題背景」「プロジェクトのねらい」「競合との位置づけ」などを詳細に語ってしまうケースがあります。
調査目的の説明でするべきでないこと
- 「新しい商品開発で…」
- 「競合との差別化を検討していて…」
- 「若年層向けの戦略で…」
こうした説明は、参加者に親切に見えるかもしれませんが、実際には忖度を生み、自然な発話を阻害します。参加者は「求められていそうな回答」を探し始め、生活者としての視点が損なわれます。しかし筆者は、目的説明はむしろ簡潔に、「何のために話を聞いているか」という方向性だけを伝えるべきだと考えています。
例えば筆者は以下のようにインタビューの趣旨説明をしています。
インタビュー調査の冒頭の例
私の仕事は、皆さんからお話を伺いして新しい商品やサービスの開発、今ある商品やサービスの改善などといったことのヒントになればいいかな、という趣旨でお話を聞くことです。こういう風にお伝えすると「いいことを言わなくては」「気の利いたことを言わないと」と構えてしまう方もいらっしゃいますが、正解はありませんので、私の質問に対して感じたことや思ったことをそのまま、率直にお話しいただけると助かります。
こう伝えることで、参加者は「企業へ合わせなければ」という気負いをせず、自分自身の感覚や経験をもとに語ってくれます。方向性は伝えつつ、具体的な狙いは語らない構造です。
冗長な背景説明は忖度や過度な気遣いを生み、本来の価値観や行動理由を見えづらくしてしまいます。
フォーカスグループでは冒頭15分が最適
筆者はフォーカスグループ(120分)を進行する際、冒頭を15分以内にすることを目安にしています。
- 自己紹介
- 目的説明
- 軽いアイスブレイク
これらを過不足なく収めると、参加者のリズムが整い、本題の議論が滑らかに進みます。
自己紹介が長すぎると重くなり、短すぎると距離が縮まりません。15分はそのバランスが最も良いと筆者は感じています。
冒頭の出来栄えは、インタビュー参加者の姿勢に現れる
筆者は冒頭の出来栄えを、参加者の姿勢で判断します。
良い冒頭では、参加者の肩が自然に落ち、声が安定し、話題が広がりやすくなります。場に無理がなく、発話のテンポが軽やかです。
悪い冒頭では、視線が泳ぎ、言葉が詰まり、発言が短くなります。参加者の思考が「正しい答え」を探す方に寄ってしまうのです。
筆者は、冒頭が整った場ほど、本題が驚くほど進めやすくなる経験を重ねてきました。
インタビューの冒頭は、調査に対する姿勢・思想が表れるプロセス
筆者は、冒頭で何を話し、何を話さないかが、定性調査の本質の部分を決めると感じています。
生活者が語りやすい状態をどう準備するか、発話の入り口をどう軽くするか、忖度をどう取り除くか。これらは単なるテクニックではなく、インタビュー全体の思想そのものです。
筆者は、インタビューフローの冒頭を設計するときに次の3点を大切にしています。
インタビュー調査の冒頭で重要なこと
- 心理的な安心感をつくる
- 事実情報のみで場の空気を整える
- 目的説明は方向性だけにとどめる
この3つが揃うと、参加者は自然な言葉を取り戻し、深い価値観や行動理由を語ってくれます。
そして企業が本当に必要とするインサイトは、その自然な語りの中からしか生まれません。
まとめ:調査冒頭にもモデレーターの手腕が問われる
インタビューの冒頭部分の設計は、調査の成否を左右する重要な工程と言っても過言ではありません。丁寧すぎる説明や抽象的な質問は、思わぬ形で参加者の発話を歪めてしまいます。だからこそ、筆者は「話しやすさ」と「自然さ」を最優先にしながら、適切な情報量と関係性づくりを意識して設計しています。
生活者の発言からインサイトを抽出するためには、冒頭でどれだけ生活者を自然体に導けるかがすべての起点になると筆者は考えています。
本稿がマーケティングリサーチ・定性調査に携わる方々の参考になれば幸いです。もし、プロのモデレーターに定性調査を相談してみたい方はリサートまでお問い合わせください。
リサートにモデレーターを派遣してもらう
この記事の監修者

石崎 健人 | 株式会社バイデンハウス マネージング・ディレクター
リサート所属モデレーター。外資系コンサルティング・ファーム等を経て現職。バイデンハウスの消費財、ラグジュアリー、テクノロジー領域のリーダーシップ。生活者への鋭い観察眼と洞察力を強みに、生活者インサイトの提供を得意とする。2022年より株式会社バイデンハウス代表取締役。2025年よりインタビュールーム株式会社(リサート)取締役。アドタイにてZ世代の誤解とリアル。「ビーリアルな、密着エスノ記」連載中。
この記事を書いた人

角 泰範 | マーケティング・リサーチャー
リサート所属モデレーター。シンクタンク・マーケティングリサーチ複数社を経て現職。マーケティングリサーチャーとして10年以上の経験を有し、大手ブランドの広範な商材・サービスの調査を支援。統計学的な分析手法とインタビューをハイブリッドに活用した、定量・定性の両軸での消費者分析力が強み。